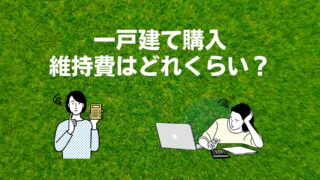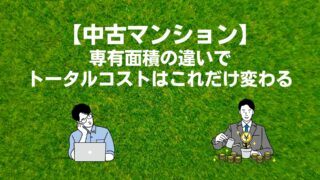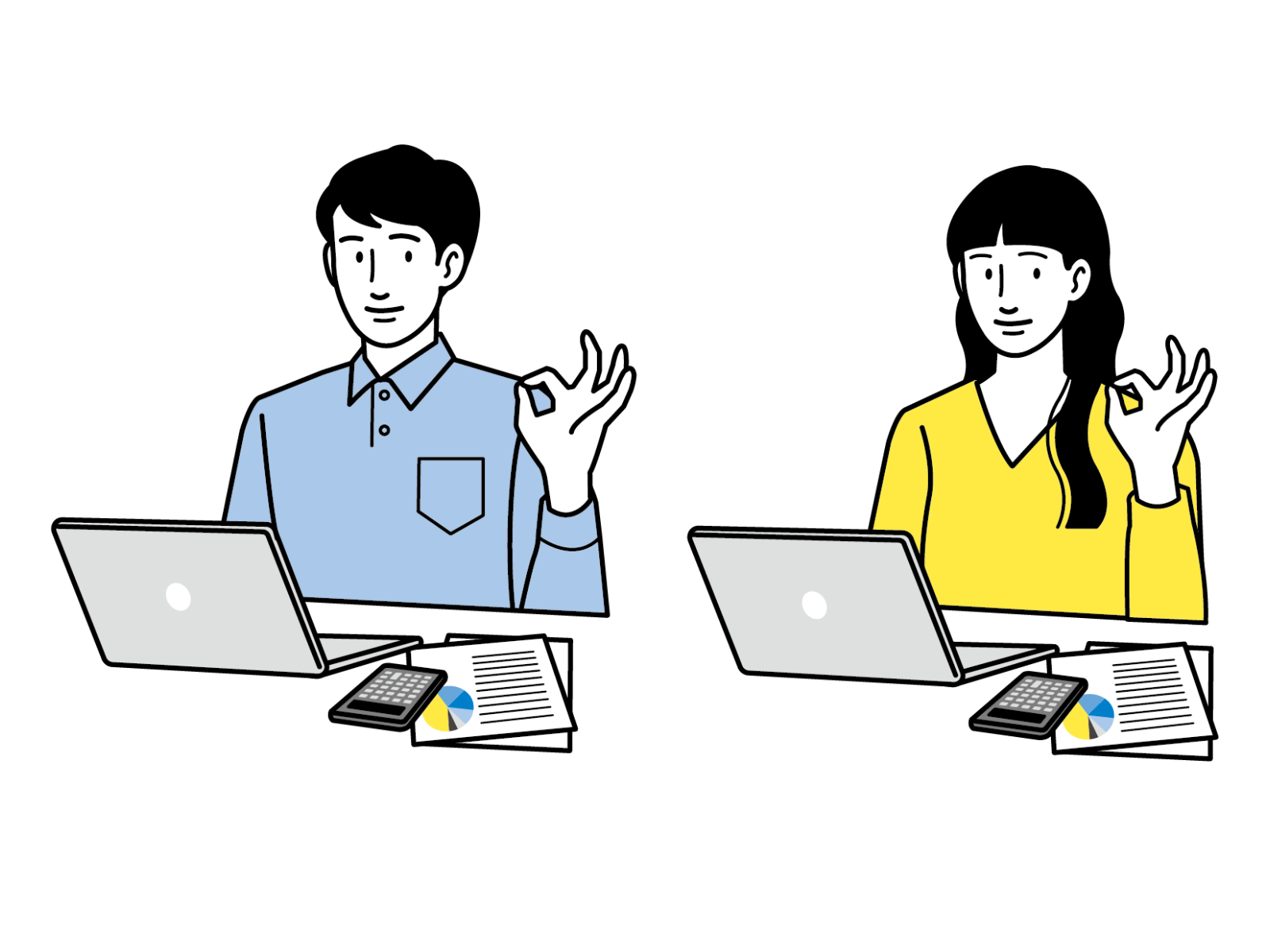投稿日:2022年3月5日 | 最終更新日:2024年11月21日
家の広さはどれくらい必要?
コロナ感染拡大以降、リモートワークの普及、外出制限による在宅時間の増加もあり、家の広さをきっかけにマイホームを購入される方もいます。
- もっと広い家に住みたい
- 部屋数を増やしたい
- 書斎・作業スペースが欲しい
- 収納を増やしたい
その一方、家を買ったあと後悔される方も…。
- もう少し広い家が良かった
- 逆に家が広すぎた
- 部屋数を考えるべきだった
この記事では家の広さについて解説します。
●理想的な家の広さ
●家の広さをみるときの注意点
●家の広さで後悔しないためのポイント
家の広さの目安
家の広さは予算や家族構成の変化、ライフプランなども踏まえながら考える必要があります。
ここでは、家の広さに関する国の指針や実際に購入・建てられている家から広さの目安について解説します。
国が考える家の大きさ
平成23年、国は「住生活基本計画」で世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現と多様なライフスタイルに対応するために必要と考えられる住宅面積の水準(誘導居住面積水準)を示しています。
誘導居住面積水準には、都市部の集合住宅を想定したものと郊外の一戸建てを想定したものがあります。
●郊外の戸建て住宅を想定
「一般型誘導居住面積」
●都市部の共同住宅(マンション)想定
「都市居住型誘導居住面積」
それぞれについて順に解説します。
一般型(戸建て)誘導居住面積水準
郊外の戸建て住宅を想定した住居面積の算出方法は以下の通りです。
●単身者:55㎡
●2人以上の世帯:25㎡×世帯人数+25㎡
世帯人数別にまとめると以下のようになります。
| 世帯数 | 誘導居住面積(㎡) |
|---|---|
| 単身者 | 55 |
| 2人世帯 | 75 |
| 3人世帯 | 100 |
| 4人世帯 | 125 |
※上記における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人として算定しますが、持ち家を想定しているため10歳以上で算出。
都市居住型(マンション)誘導居住面積水準
都市部のマンションを想定した住居面積の算出方法は以下のとおりです。
●単身者:40㎡
●2人以上の世帯:20㎡×世帯人数+15㎡
| 世帯数 | 居住面積(㎡) |
|---|---|
| 単身者 | 40 |
| 2人世帯 | 55 |
| 3人世帯 | 75 |
| 4人世帯 | 95 |
マンションで4人家族の場合、都市部で95㎡となると流通する物件数や予算的に考えるとハードルは高そうです。
これを見ると、一戸建てとマンションでは、1人当たりの誘導居住面積に差があります。
●一戸建て:約31~37㎡/人
●マンション:約23~28㎡/人
では、この国の考える基準に対して、実際にはどれくらいの広さの家を購入あるいは建てられているのでしょうか。
家の広さの平均
下表は、住宅の種類別の住宅面積と家族数の全国平均値を表にしたものです。
| 住宅の種類 | 住宅面積 (㎡) | 家族数 (人) | 1人当たり 住宅面積 |
|---|---|---|---|
| 注文住宅※ | 122.8 | 3.6 | 34.1 |
| 土地付き 注文住宅 | 111.5 | 3.3 | 33.7 |
| 建売住宅 | 101.9 | 3.2 | 31.8 |
| マンション | 65.7 | 2.4 | 27.3 |
| 中古戸建て | 114.2 | 3.1 | 36.8 |
| 中古マンション | 68.0 | 2.5 | 27.2 |
※注文住宅は建物のみ住宅ローンを利用した人、土地付き注文住宅は土地を含め住宅ローン利用した人です
戸建ての家の広さ
戸建ては、平均3~4人の家族構成に対して100~120㎡の広さになっています。1人当たりの住宅面積でみると、31~37㎡/人となっており、国の基準に近くなっています。
建売住宅が他と比べてかなり広さが少ない傾向です。
マンションの家の広さ
マンションは、平均2~3人の家族構成に対して65~70㎡となっています。国が示す居住誘導面積(75㎡~95㎡)と比べると狭い現実ですが、1人当たりの居住面積では約27㎡/7人と国の示す基準の範囲内におさまっています。
このデータは購入時点の家族人数をベースにしていますので、将来的に家族が増えると基準を下回るかもしれません。
住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」(2022年度)
家の広さをみるときの注意点
床面積、専有面積と有効面積
物件資料やポータルサイトをはじめネット上で表示される床面積や専有面積をみるときに注意すべき点について解説します。
家の広さを表す際、一戸建てとマンションで以下の表現を使います
●戸建て:延床面積
(各階の床面積合計)
●マンション:専有面積
一戸建ての延床面積
一戸建ての建物や部屋の広さを表現する単位として、「㎡」以外に「坪」「畳」などが使われます。
これらの単位が表す広さや販売図面などを見る際、延床面積に含まれないものを知っておくことも大切です。
「1坪」・「1畳」の広さ
1坪=約3.31㎡=約2畳
| 25坪 | 約82.7㎡ | 約50畳 |
| 30坪 | 約99.3㎡ | 約60畳 |
| 35坪 | 約115.8㎡ | 約70畳 |
| 40坪 | 約132.4㎡ | 約80畳 |
畳1枚の広さは地域によって違いがありますが、不動産取引上のルールでは、畳1枚当たり1.62㎡以上であることが必要となっています。
住宅の居室等の広さを畳数で表示する場合においては、畳1枚当たりの広さは1.62平方メートル(各室の壁心面積を畳数で除した数値)以上の広さがあるという意味で用いること。
不動産公正取引協議会連合会「不動産の表示に関する公正競争規約」
延床面積に含まれないもの
延床面積は、建物すべての階の床面積を合計したものですが、建築基準法上延床面積に含まれないものがあります。
延床面積に含まれない、つまり容積率に含まれないものを知ることで、間取りを考えるうえでも参考になります。
容積率
建物の延床面積の敷地面積に占める割合
●バルコニー・ベランダ
外壁から2mまでは延床面積に含まれません。逆に言うと、2mを超える部分は床面積に含まれます。
●吹き抜け
吹き抜けの上階部分は床面積には含まれません
●ロフト(小屋裏収納)
以下の条件を満たすことで延べ床面積には含まれません。
- 天井高1.4m以下
- 面積が設置する階の床面積の1/2以下
- はしごが固定されていない
●ビルトインガレージ
家の内部にあるビルトインガレージは、延床面積の1/5以内のものは緩和措置の対象となり延床面積に含まれません。1/5超える部分については延床面積に算入されます。
●出窓
以下の条件を満たすことで延べ床面積には含まれません。
- 床面から出窓下までの高さ30cm以上
- 外壁面からの水平距離50cm未満
- 見付け面積の1/2以上が窓
マンションの専有面積
マンションの専有面積には、壁芯面積(壁の中心線)と内法面積(壁の内側)があります。
当然ですが、内法面積は壁芯面積より小さくなります。
居住空間の有効性で考える場合、内法面積になりますが、マンション販売図面や広告は、壁芯面積で記載されることが多いです。
登記簿謄本の面積の表示は内法面積となっています
マンションは、木造の一戸建て住宅と比べて壁厚や柱の断面は大きくなります。
つまり、一戸建て以上に壁芯面積と内法面積の差が生じやすいということです。
マンションの有効面積は、物件資料(壁芯面積)の3~5%程度少なく見積もるか、登記簿謄本で確認するようにしましょう。
一戸建てとマンション有効面積の違い
一戸建てとマンションを比べた場合、2階、3階建ての一戸建ての床面積には階段室が含まれます。(下図赤枠部分)
ですので、一般的には同じ広さでも、生活スペースの有効面積は、階段室がないワンフロアのマンションがより広くなります。

また、これは一戸建てにもマンションにも言えることですが、間取りの廊下部分(下図赤色部)や生活動線上、通路的な使い方、デッドスペースが生じる場合があります。(下図緑色部)

通路は必要ですが、間取り的に通路やデッドスペースが多いほど、実質的に使える有効面積は少なくなります。
間取りをチェックする上で、生活動線とともにデッドスペースもしっかりチェックすることが必要です。
家の広さで後悔しないポイント
最後に、家の広さで後悔しないためのポイントについて解説します。
家の広さに応じた維持費がかかる
広い家を買うと、購入資金だけでなく購入後の維持費も増えます。
戸建ての場合、広い家であればあるほど、屋根や外壁の面積も増え、修繕やメンテンナンス費用は多くかかります。
また、ほとんどのマンションでは、専有面積の広さに応じて管理費や修繕積立金が決まります。
75㎡と90㎡のマンションでは、毎月の維持費が1.25倍違うことになりますし、固定資産税も高くなります。
そのため、家の広さを考えるうでも、購入価格だけでなく維持費も含めて判断が必要です。
マンションの修繕積立金は、築年経過とともに上がることを想定しておきましょう。
子どもの独立や老後のライフプランとの関係
家の広さを考えるうえで、間取り(部屋数)も含めて、子どもの独立後のことや老後のことも考えて家の広さを決めたほうがよいでしょう。
子どもが独立後、家の広さや部屋数をもてあましてしまうことはよくあります。
子どもの住環境を考えるという意味では、購入時の子どもの年齢も大切です。子どもが進学や独立して家を出るまでの期間、つまりその家で過ごす期間が長ければ長いほど、子どものための部屋やスペースを考える意味は大きくなります。
また、住んでいる地域によって進学や就職で家を出る可能性も異なるかもしれません。
なかなか将来のことを見通すことは簡単ではありませんが、将来の住み替えやライフプランを含めて考えると選ぶ家の広さや間取りも変わるかもしれません。
まとめ
家の広さについて解説しました。
●今より住環境をよくしたい
●良い住環境を子どもに与えたい
こういった場合、一定の広さが欲しくなるのも当然です。
ただ、家が広ければ価格は高くなりますので、その分、土地や立地条件に影響することもあります。
維持費との関係、将来のライフプランなども踏まえて判断することをおすすめします。