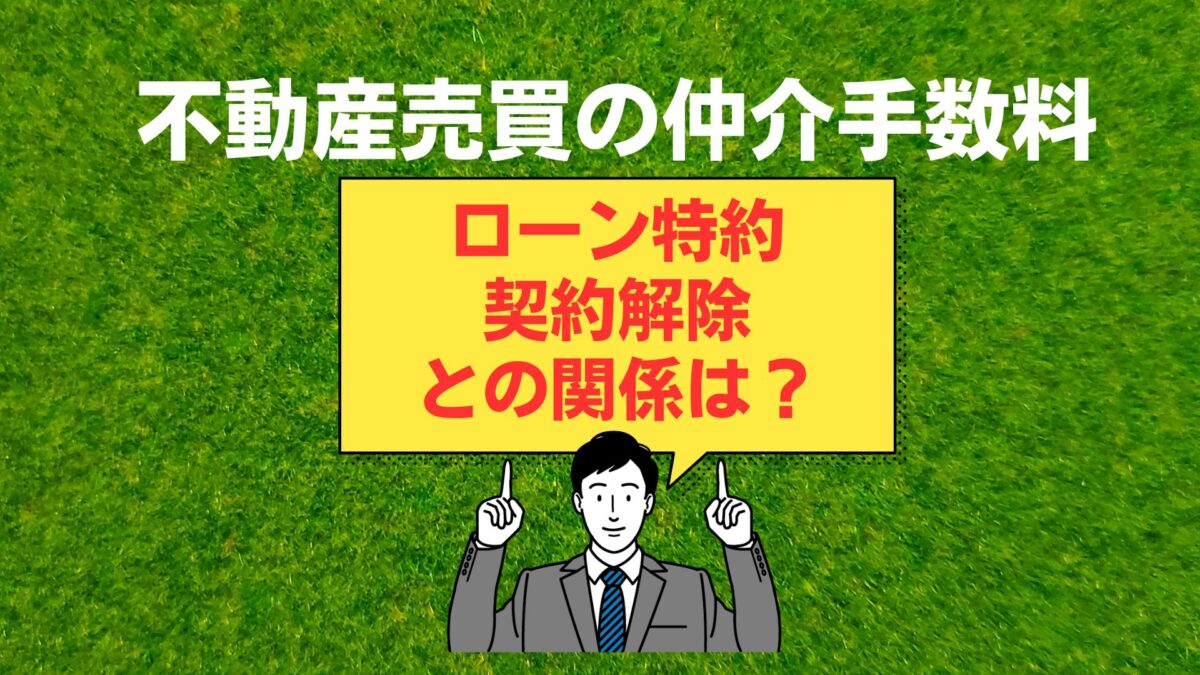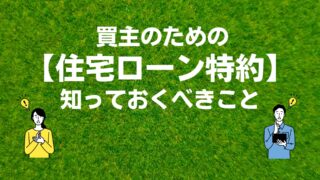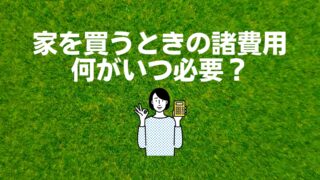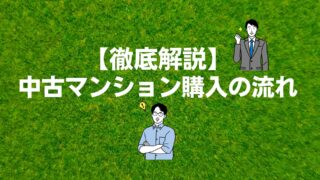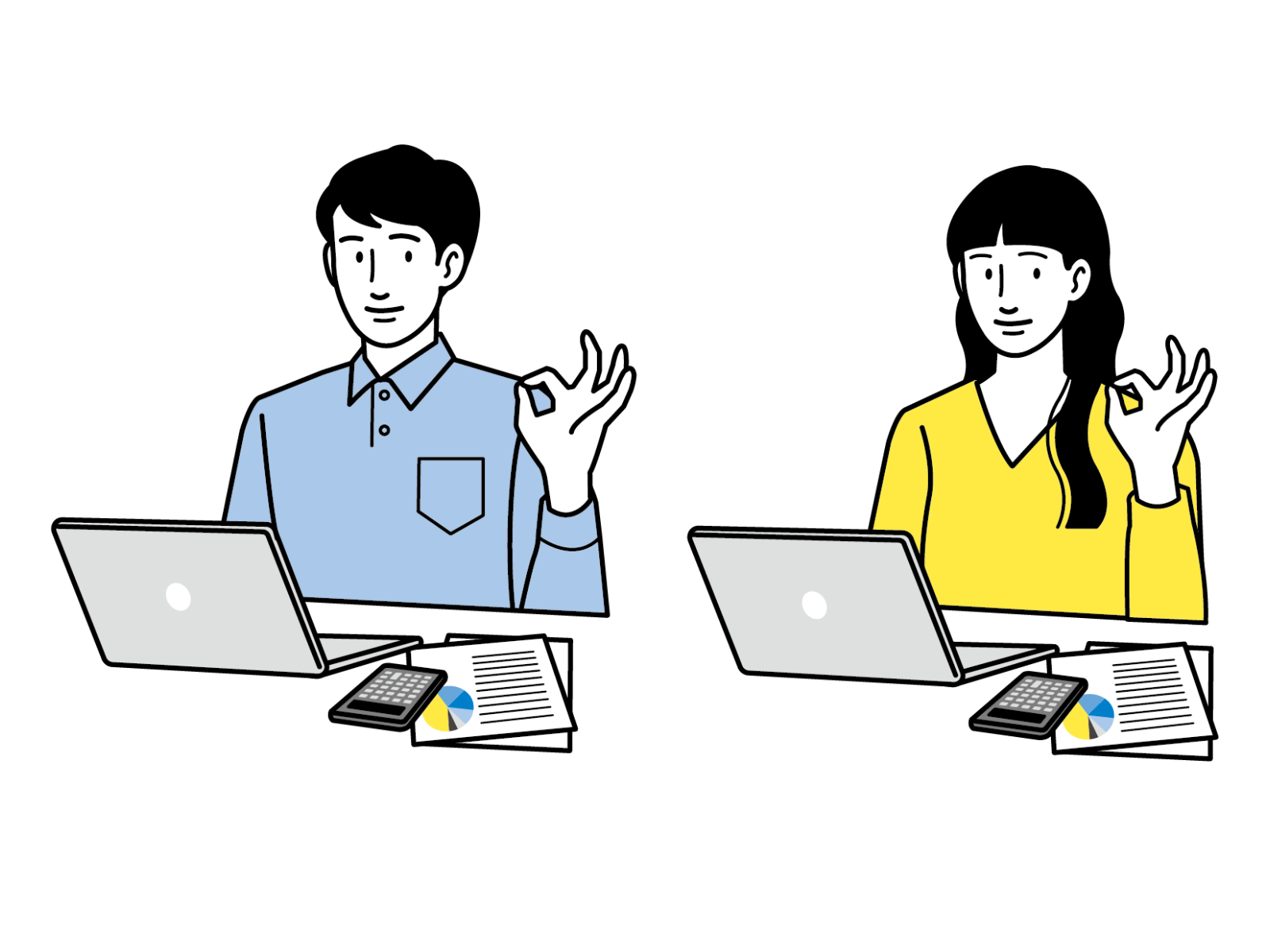投稿日:2020年3月19日 | 最終更新日:2024年11月21日
仲介手数料とは
仲介手数料は、
不動産を購入・売却する際に売主と買主の間に不動産会社が入り、物件の内見や売買契約手続き、重要事項説明の事務、住宅ローンのサポートなどの業務に対して支払う手数料です。
例えば、個人の売主さん、買主さんが、個人間だけで売買することは法律上可能です。
ただ、現実問題として、買主を見つけるのは簡単ではありません。
また、仮に見つかっても、不動産売買には、契約書や重要事項の作成、住宅ローン、火災保険、税金といった専門的なことが関係します。
ですので、個人間で不動産取引を引渡しまで、問題の発生なくすすめるのは難しいことです。
つまり、仲介手数料は、売主と買主の取引の安全を担保するための費用とも言えます。
この記事では、仲介手数料について、
- 金額
- 請求できる時期
- 売買契約上の取扱い
買主の視点でまとめました。
仲介手数料の額
仲介手数料の額は、法律で規定されています。
(宅地建物取引業法46条および国土交通省の報酬に関する告示)
| 契約金額 | 仲介手数料 |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 契約金額×5%+税 |
| 200万円超え400万円以下部分 | 契約金額×4%+税 |
| 400万円を超える部分 | 契約金額×3%+税 |
簡易的な計算方法は以下のとおりです。
物件価格400万円以上の場合、
『 物件価格×3%+6万円+消費税 』
これは仲介手数料の上限金額でこの金額を超えて請求することは違法です。
仲介手数料と媒介契約
仲介手数料の根拠となるのは、不動産会社と買主(あるいは売主)の間で取り交わされる媒介契約です。
媒介契約書には、仲介手数料報酬の額、支払時期などが明記されています。
また、仲介手数料は、
売買契約成立に対する成功報酬
です。
つまり、売買契約が成立しなければ仲介手数料は発生しません。
仲介手数料が請求できる時期
仲介手数料は、売買契約が成立した時点で不動産仲介会社に請求権が発生します。
【不動産取引の一般的な流れ】
1、物件探し
2、不動産購入申込
(購入の意思表示)
3、売買契約成立(仲介手数料の請求が可能)
4、住宅ローン契約(金銭消費貸借契約)
5、引渡し・決済
ただ、不動産取引の場合、売買契約が成立しても決済・引渡しまでには時間を要します。
ですので、多くの不動産会社では、
売買契約成立時点で仲介手数料の半額を請求、残りを引渡し時に請求する
という形をとっています。
売買契約が解除された場合
では、売買契約成立後、引渡し(決済)までに何らかの理由で契約解除になった場合、仲介手数料の取扱いはどうなるのでしょうか。
- 住宅ローン特約による解除
- 買主都合による解除
- 売主都合による解除
それぞれの取扱いをまとめました。
住宅ローン(融資)特約
住宅ローン特約
住宅ローンの借入を前提に購入する買主が、住宅ローンの借入ができなかった場合、あるいは必要な金額の借入ができなかった場合に、違約金などの負担なく売買契約を無条件で契約を解除できる約定。
売買契約が成立すると、
・売主には期日までに物件を引渡す
・買主には売買代金を支払う
契約上の義務が生じます。
この義務を果たせない場合、債務不履行となり損害賠償責任を負います。
ただ、住宅ローンの融資を前提に売買契約を締結し、融資を受けるために積極的に行動したにも関わらず、結果的に融資が下りない場合にも、買主に債務不履行責任を負わせるのは酷です。
そこで、買主保護のため、売買契約上の特約として「住宅ローン特約」が設けられています。
住宅ローン特約による契約解除と仲介手数料
では、住宅ローン特約により売買契約が解除された場合、仲介手数料の取り扱いはどうなるのでしょうか?
まず、住宅ローン特約により売買契約が解除された場合、売主は買主に対して受け取った手付金を無利息で返還する必要があります。
そして、仲介手数料は、
住宅ローン特約による解除の場合、支払う必要はありません。
ですので、不動産会社がすでに受け取った仲介手数料は、無条件で買主に返還する必要があります。
この点は、媒介契約書にも記載されているはずですので確認しましょう。
自己都合による解除(手付解除など)と仲介手数料
不動産売買契約では、金額の大きな取引を行う上で、売主・買主には、手付解除の権利が設けられています。
つまり、売買契約後、買主は支払った手付金を放棄し、一方の売主は受領した手付金の倍額を支払うことで売買契約を解除することができます。
手付解除があることで、売買契約締結後でも
・やっぱり家を買うのはやめよう
・住宅ローンは組みたくない
といった自己都合でも契約を解除することができます。
この場合、不動産会社に落ち度がないにも関わらず、自己都合で一方的に契約を解除されて仲介手数料が請求できないとなるのは不合理です。
ですので、手付解除により売買契約自体は無効になっても、売買契約は成立している以上、仲介手数料の請求権が発生します。
ですので、手付解除など自己都合による契約解除の場合、
不動産会社は仲介手数料を請求することができます。
過去裁判例でも仲介手数料の請求が認められています。
仲介手数料全額を請求できるのか?
ただ、この場合、
仲介手数料全額を請求できるか?
という問題はあります。
宅地建物取引業法では、不動産仲介業務として、売買契約成立後の決済、引渡しまでの事務をサポートすものとなっています。
売買契約が引渡し前に解除された場合、その後のサポートする事務も発生しません。
こういった状況も想定し、国土交通省は、仲介手数料は、売買契約成立時に半金、引渡し時に残りの半金を請求すべきとしています。
とすると、買主の自己都合で契約解除になった場合、契約成立までの報酬として仲介手数料の半金を請求できるという考え方もできます。
ただ、どれくらい請求できるかは明確にはなっておらずグレーな部分です。
媒介契約書で規定されている場合は別として、自己都合による契約解除の場合でも、
仲介手数料の全額を当然に支払わなければならないわけではない
ことは知っておきましょう。
売主都合、違約による契約解除と仲介手数料
では、契約の相手方の都合、もしくは違約によって解除になった場合、仲介手数料はどうなるのでしょうか。
この場合、買主自身には何の責任もないのに、契約を解除された上、仲介手数料まで支払わなければならないとすると酷とも思えます。
ただ一方で、売主側の手付解除においては、手付金の倍額を受け取ります。
つまり、買主は手付金相当額を受け取ることができます。
また、売主の違約による解除になった場合、売買契約上の規定に応じて、違約金(損害賠償)を受け取ることができます。
ですので、手付金や違約金の額に応じて、仲介手数料を請求できるという内容となっていることもあります。
まとめ
仲介手数料を支払う時期
売買契約時に半金、引渡し時に残り半金
(取り決めによって引渡し時に全額支払いも可)
売買契約解除と仲介手数料の取扱い
①住宅ローン特約による解除
⇒仲介手数料の支払い義務なし
②自己都合による手付解除
⇒仲介手数料の支払う場合あり
※但し、当然に全額を支払う必要があるかは別
③売主の都合、違約解除
⇒手付金、違約金の額に応じて支払う場合あり
事前に不動産会社との媒介契約書、売買契約書の内容をしっかりと確認してください。