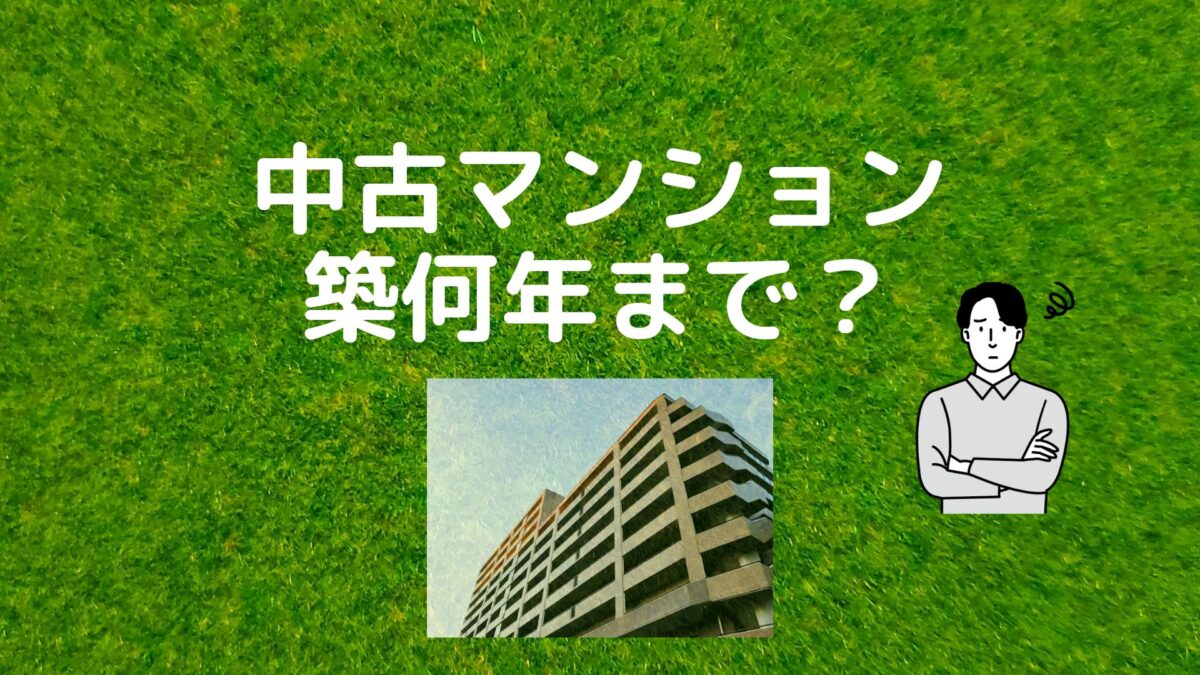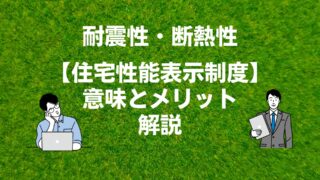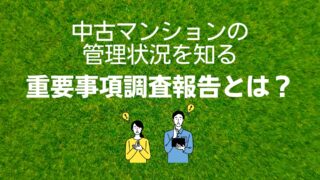投稿日:2022年9月12日 | 最終更新日:2024年11月21日
はじめに
中古マンションを探すなかで、築年数はとても気になると思います。
- 築10年以内で探したいが予算的に難しい
- 住み続けることを考えたら築年数は20年まで
など考えるものの、なかなか予算内で気に入った物件が見つからない方も多いのではないでしょうか。
・値段が下がりにくいのは築何年のマンション?
・築年数の経過したマンションでもずっと住めるの?
・築年数によって何が違うの?
・将来、住み替えなどで売却するときに売れるの?
・住宅ローンは問題なく借りられる?
この記事ではこういった疑問について解説します。
築年数からみたマンションの買い時は?
中古マンションの築年数で買い時といえるのは築何年なのでしょうか。
ここでは、次の2つの視点からマンションの買い時について解説します。
・価格や資産性からみた買い時
・耐震性など住宅性能からみた買い時
中古マンションの築年数と価格、資産性との関係
マンションの築年が経過すればするほど、当然価格は下がります。
下図は、近畿圏で2021年度に取引された中古マンションの築年数と価格(㎡単価)、下落率の関係を表したです。
| 築年数 | 価格(万円/㎡) | 下落率 |
|---|---|---|
| ~築5年 | 66.49万円 | - |
| 築6~10年 | 58.80万円 | 11.5% |
| 築11~15年 | 48.17万円 | 18.1% |
| 築16~20年 | 42.93万円 | 10.8% |
| 築21~25年 | 32.67万円 | 23.2% |
| 築26~30年 | 20.89万円 | 36.0% |
| 築31~35年 | 23.90万円 | +14.4% |
| 築36年以降 | 20.63万円 | 13.6% |
これをみると、中古マンションの価格は、
築26~30年で下げ止まり、
築31年以降は、上昇もしくは横這い
この傾向は、近畿地域だけでなく他の地域でもみられ、また2020年以前でも同様の傾向です。
つまり、築年数と価格の関係でいうと、築25年くらいから価格は下がりにくくなるということです。
新築で購入した場合、平均的には築25年までは資産価値は下がり続けることになります。
また、下落率でみると、築16年~25年にかけての下落率がもっとも大きくなっています。
ですので、築年数と価格の関係をまとめると
築15年くらいまでは緩やかに価格は下がり、
その後、築16年から25年に下落率が大きくなるものの、
それ以降は下がりにくい傾向といえます。
これをみると、価格面だけで考えると築25年あたりのマンションが買い時といえます。
近畿不動産流通機構 2021年市況レポート
(近畿レインズ)
築年数による耐震性・住宅性能の違い
次に、価格や資産性といったお金の面ではなく、住みごこちにも関係する住宅性能や耐震性といった点からみた買い時についてです。
築年数によって、建てられるマンションの基準がどのように変わり、耐震性や住宅性能にどう影響してきたのかをまとめました。
1970年代
1970年代のマンションは、耐震基準としては旧耐震基準となります。
コンクリートのスラブ厚も現在の標準(20cm)と比べると12~15cmとうすく、また、電気や給排水管がスラブの中に埋め込まれているマンションも少なくありませんでした。
1980年代
1981年6月に旧耐震基準から新耐震基準への建築基準法の改正があります。
新耐震基準では、
- 震度5強程度の地震ではほとんど損傷しない
- 震度6強から7程度の地震で倒壊・崩壊しない
耐震性能が求められました。
スラブ厚は18cmが標準となり、排水管も床下へ通すようになりました。
間取りが多様になってきたのもこの時代からで、現在でも主流の「田の字型」から「センターイン型」などのコスト的には高い間取りも普及しました。
バブル経済を背景として、投資用マンションが登場したのもこの時代です。
新耐震基準が適用される建物は、
1981年6月1日以降に確認申請を受けた建物です。
※マンションは建築工期が1年以上必要ですので、1981年以降完成した建物でも旧耐震基準である可能性がありますので微妙な時期は確認が必要です。
1990年代
1991年のバブル経済の崩壊によってマンション価格が下がった時代です。
1990年代後半になると、機能性が重視されるようになり、二重床や二重天井が登場し階高も3mが標準的になってきます。
バリアフリーが重要視されたのもこの時代で、システムキッチンやユニットバスなどの住宅設備が充実し、宅配ロッカーやキッズルームなどマンション共用施設や設備が多様化していきました。
2000年代
2000年代に入り、いくつか住宅性能について法律改正がありました。
2000年4月 住宅の品質確保の促進等に関する法律
2000年10月、住宅性能表示制度は、2000年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」にもとづき始まった制度です。
- 構造の安定(耐震等級など)
- 火災時の安全(警報装置や避難経路など)
- 劣化の軽減(スラブ厚や錆対策など)
- 維持管理・更新への配慮(配管の更新など)
- 温熱環境(省エネ対策等級など)
- 空気環境(換気対策など)
- 光・視環境(開口部の床面積に対する割合など)
- 音環境(床遮音性など)
- 高齢者等への配慮(移動の安全性など)
- 防犯(侵入防止対策など)
10分野に対する評価でできています。
この制度以降の建物は、
設計段階と建設段階で建物性能を評価する「住宅性能評価書」が付与されている可能性があります。
2003年7月 シックハウス対策の義務化
建築基準法が改正され、シックハウス対策が義務化。
当時「シックハウス症候群」といって、住宅の気密化・断熱化が高度になると同時に、新建材と呼ばれる化学物質を含有した材料を使うことにより、室内の空気が化学物質などに汚染され、人体に悪影響を与える症状が問題となりました。
この改正により、2003年7月1日以降に着工する住宅に対して、
- 規制対象とする化学物質の明確化。
→特定の化学物質を含む建材の使用禁止。 - (代表的な化学物質である)ホルムアルデヒドを発散する内装材の制限
- 24時間換気システムの義務付け
などが規定されました。
ただし、この改正で規制される物質は、
「ホルムアルデヒド」「クロルピリホス」です。
空気汚染の原因となる物質全てが規制されたわけではありません。
2007年6月 建築基準法ならびに建築士法の改正
2005年に発覚した構造計算の偽装問題をきっかけに建築基準法および建築士法が改正されました。
一定の高さ以上の建築物について、
- 建築確認・検査の厳格化
- 建築確認や審査を行う民間検査機関に対する指導監督の強化
- 建築士に対する罰則強化
第三者機関の専門家による構造審査や特定の住宅に対する中間検査が義務付けられました。
2008年7月 長期優良住宅の普及の促進に関する法律
長期優良住宅認定制度は、2008年に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」にもどづくものです。
- 耐震性
- 劣化対策
- 維持管理・更新の容易性
- 可変性(共同住宅)
- 住戸面積(一戸建て75㎡以上など)
- 省エネルギー性 ※断熱等性能等級4など
- 居住環境
- 維持保全管理※少なくとも10年ごとに点検を実施
などので一定の条件を満たした建物は、長期優良住宅として認定され、税制面や住宅ローンにおいて優遇措置が受けられることになりました。
新築住宅については、2009年6月より認定が始まっています。
2000年に入り、住宅性能や耐震性を左右する法律改正と認定制度ができました。
もちろん、これらの認定制度があっても、すべての建物が認定を受けているわけではありません。
ただ、これらの制度以降に建てられた物件は、住宅性能を評価、向上させることで、より安全な不動産取引の促進やより長期間の使用に耐えうる住宅をつくろうという機運がある中で建てられた物件であるといえます。
ですので、住宅性能や耐震性といった点から買い時を判断すると、
・旧耐震から新耐震基準に変わった1981年
・住宅性能を担保する制度が普及した2000年以降
が1つの基準と考えることもできます。
旧耐震基準で建てられたマンションでも、耐震改修工事を実施し耐震性が上がっているものもありますが、一方で耐震改修工事をしたからといって必ずしも新耐震基準以上の耐震性が確保されているとは限らない点には注意してください。
マンション築年数の限界は?どうやって決まる?
では、築年数の経過したマンションはいつまで住めるのでしょうか?
ここでは、築年数による構造的な限界、給排水管等の設備、維持管理上の限界、そして管理組合の活動としての限界含め解説します。
構造的にみたマンションの限界は築何年まで?
マンション(RC造、SRC造)の税法上、減価償却資産としてみた場合の耐用年数は47年です。
| 構造 | 耐用年数 |
|---|---|
| 鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 47年 |
| 木造 | 22年 |
| 軽量鉄骨 | 19年~34年 (鋼材厚による) |
これはあくまで税法上の償却期間としてみた場合の耐用年数です。マンションの構造的な限界については、
さまざまな見解がありますが、国土交通省「中古住宅流通促進・活用に関する研究会」報告書では、以下のような提言がされています。
・鉄筋コンクリ-ト造建物の物理的寿命を117年
・耐用年数は120年。定期的な修繕を実施することで150年
・固定資産台帳の滅失データから56年
これらをみると、物理的には大規模修繕などをしっかり行えば100年でも構造的には問題ないともいえますが、やはり大切なのは維持管理、メンテナンスが行わているかになります。
国土交通省「中古住宅流通促進・活用に関する研究会」(平成25年9月26日)の報告書
マンションの配管の限界・交換
マンションの場合、給排水管の寿命や更新がマンション自体の寿命にも影響します。
給排水管の寿命
下表は、配管の種類と寿命、使用時期をまとめたものです。
| 配管種類 | 寿命(目安) | 使用時期 |
|---|---|---|
| 水道用亜鉛メッキ鋼管 ※現在では上水道での使用は禁止 | 15〜20年 | ~1970年 |
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | 〜30年 | 1970年~ |
| ステンレス鋼管 | 半永久的 | 1980年~ |
配管の寿命の目安はありますが、実際はマンションの建設時期によって、給水管に使用されている管材や継手の種類、配管施工方法は異なりますし、給水管の使用状況や水質もマンションごとに異なるため、給水管の耐用年数にはかなり差が出ます。
給排水管の交換・メンテナンス方法
給排水管のメンテナンス、交換をするにしても、配管の場所や施工方法によって変わります。
まず、マンションの場合「専有部分」と「共用部分」があり、専有部分の配管は所有者が維持管理する必要がありますし、必要なときに工事、メンテナンスができます。
一方共用部分の配管は、管理組合の区分所有者全員で共有していますので、維持管理は管理組合の修繕計画に基づいて行われます。
また、配管の施工方法によって、配管工事の難易度は異なります。
マンション専有部分の配管の施工方法には、「床スラブ上配管」と「床スラブ貫通配管」があります。
床スラブ上配管の場合、躯体と床材の間に配管を通しているため比較的簡単に工事を行うことができます。
一方、「床スラブ貫通配管」の場合、躯体に直接床材が貼り付けられており、配管が床スラブを貫通していることから、配管自体を交換する工事は難しくなります。
築年数を経過したマンションでは、この施工方法が採用されているものもありますので、配管の維持管理方法がどのようになっているかしっかりと確認が必要です。
管理組合の活動としての限界
築年数が経過したマンションは、居住する住人すなわち管理組合を構成する年齢層も高くなる傾向です。
マンションを維持管理するためには、管理組合が正常に活動することが必要です。
下表は、平成30年マンション総合調査における、世帯主の年齢と割合を示したものです。
| 世帯主の年齢 | 割合 |
|---|---|
| 20代 | 0.4% |
| 30代 | 6.6% |
| 40代 | 18.9% |
| 50代 | 24.3% |
| 60代 | 27.0% |
| 70代 | 19.3% |
| 80代以上 | 2.9% |
平成30年の調査結果ですが、約半数が60代以上、つまり2戸に1戸が高齢世帯になっています。
さらに近い将来高齢者になる50代まで含めると約75%となります。
マンション管理組合が高齢化するリスクは以下のようなことが考えられます。
- 理事長や役員のなり手がいない
- 管理組合の活動の参加率が下がる
- 入院や施設への入所、相続による空き家率増
- 空き家率増にともなう管理費等の滞納
同調査における「管理組合の役員就任への対応」をみると、
| 回答 | 割合 |
|---|---|
| 快く引き受ける | 14.3% |
| 順番が回ってきたら引き受ける | 60.7% |
| 他になりてがいなかったらやむを得ず引き受ける | 13.8% |
| 引き受けない | 5.9% |
「順番が回ってきたら引き受ける」という回答が半数以上を占めるものの、年齢層が上がるにしたがって、「やむを得ず引き受ける」と回答する人の割合が増えています。
築年数が経過しても売買によって管理組合の新陳代謝がすすむことが理想ですが、人口減少社会のもと築年数経過にしたがってなかなか売却できない、流通しないマンションが増えてくることも予想されます。
中古マンションを選ぶうえでの注意点
最後に、中古マンションを選ぶうえでの注意点を紹介します。
住宅ローン減税・審査
築年数に関する住宅ローン減税の適用条件として、新耐震基準であることが必要となります。
令和4年度税制改正前は、原則築25年以内の物件が対象でしたが、大きく緩和され、1982年1月1日以後に建築されたものとなりました。
ただ一方で、住宅ローン審査にも築年数は影響します。
住宅ローンを借りる際、金融機関は、万一住宅ローン支払いができなくなった場合のリスクに備えて、物件に担保(抵当権)を設定します。
ですので、住宅ローン融資の可否、貸出金額に物件の担保価値が影響し、基本的には築年数が経過するほど担保評価は低くなります。
築年数だけで担保価値が決まるわけではありませんが、場合によっては、借入希望額から減額承認されたり、別途保証人を求められることもあります。
また、金融機関によって担保評価の仕方は異なります。
固定資産税評価額や路線価、公示地価に加え、法定耐用年数も評価基準となります。
その結果、年齢ではなく、物件の耐用年数と築年数から借入期間が短くなる場合もあります。
当初35年で返済計画を立てていたものが25年や30年となると、返済負担率上がり必要な借入金額に満たない場合もありますし、返済自体が難しくなることも考えられます。
そして、担保評価は借入金額に対しての評価でもありますので、諸費用やリフォーム費用など含め、
物件価格以上の借入をする場合は注意が必要です。
マンションの管理状況
「マンションは管理を買え」と言われますが、管理状況はマンションを選ぶ上で重要です。
この点、築年数が浅いマンションだと、大規模修繕工事(新築後13~17年程度)をまだ迎えておらず、修繕積立金の積立状況に対してどれくらいの費用がかかるか分かりにくいこともあります。
逆に、築15年~経過し、大規模修繕工事を実施しているマンションであれば、管理費や修繕積立金の徴収、積立状況やマンション内の問題に対して対策がされているか(工事履歴)など、確認や評価はしやすくなります。
つまり、管理状況や管理組合の活動について判断するという点では、築浅のマンションより大規模修繕を終えているマンションの方が判断がしやすいといえるかもしれません。
管理状況の確認方法や管理費、修繕積立金については、下記記事も参考にしてみてください。
住み替え等のライフプラン
・将来の住み替えを想定するか
・何年くらい先の住み替えや売却を想定するか
などによっても、築年数への考え方が変わってくるかもしれません。
将来のどこかの時点で売却や住み替えをする前提であれば、
・資産価値が落ちにくい築年数
・その時点で売却できる、しやすい築年数
といったことも踏まえて築年数やマンション選びを考える必要があります。
例えば、お子様が1人の時にマイホームを購入し、2人目のお子様をどうするか迷っていて2人目のお子様ができたら住み替えるというライフプランを考えられる方もいらっしゃいます。
そういった、近い将来の売却や住み替えを想定される場合に、価格の維持しやすさや売却のしやすさはより重要になります。
まとめ
中古マンションの築年数について解説しました。
- 価格は築25年程度で下げ止まる
- 1981年に旧耐震から新耐震基準へ変更
- 2000年以降の住宅性能や耐震性に関わる改正
- 維持管理を行うことで構造的な限界は100年
- 配管の寿命と工事方法を確認
- 住宅ローン審査への影響も考える
- 管理状況をしっかり確認する
- 住み替えなどのライフプランも踏まえて決める
マンションの築年数は、予算、住環境そして資産性にも影響する重要な要素です。
マンション探しの参考にしてみてください。