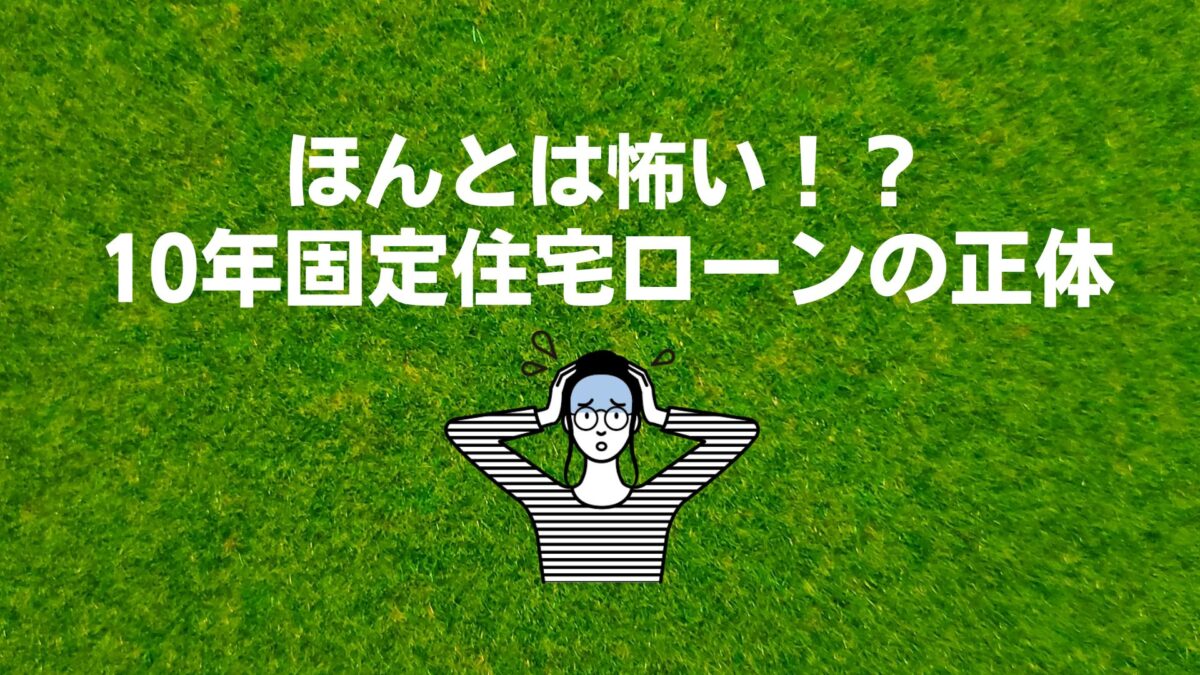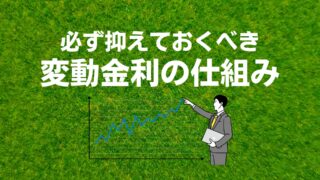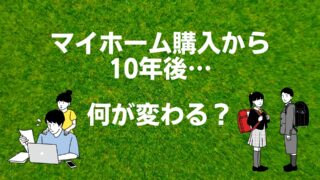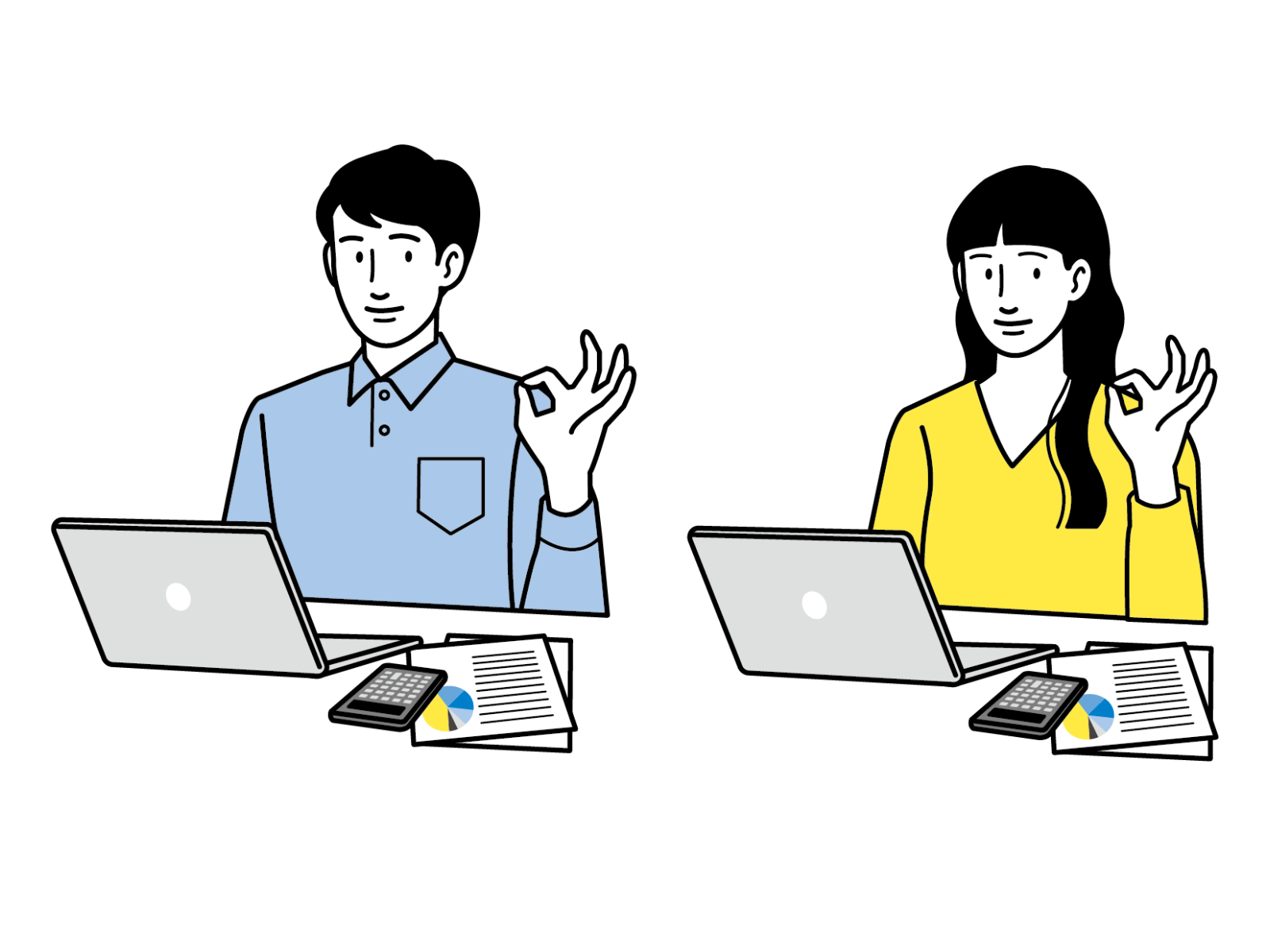投稿日:2016年7月19日 | 最終更新日:2024年11月22日
はじめに
住宅ローン金利タイプは大きく3つあります。
・変動金利
・全期間固定金利
・固定期間選択型
固定期間選択型の住宅ローンは、当初固定する期間によって、3年、5年、7年、10年、15年、20年などがあります。
そして、期間選択型の商品の中では最も選ばれているのが当初10年固定の住宅ローンです。
固定期間選択型を選ばれる方の54.9%の方が10年固定を選ばれています。
(令和2年度民間住宅ローンの実態に関する調査)
住宅ローン10年固定金利は、借入から10年間金利が固定される住宅ローンです。
10年固定住宅ローンランキング
下表は、2023年10月(地域:兵庫県)の10年固定金利の金利と金融機関の一覧表になります。
| 金融機関 | 当初10年固定金利 |
|---|---|
| 池田泉州銀行(融資手数料型) | 0.795% |
| 三菱UFJ銀行 | 0.940% |
| 山陰合同銀行 | 1.000% |
| 鳥取信用金庫 | 1.000% |
| 池田泉州銀行(保証料型) | 1.045% |
| トマト銀行 | 1.050% |
| SBI新生銀行 | 1.100% |
| 三井住友銀行 | 1.140% |
| ソニー銀行 | 1.150% |
| トマト銀行(団信保障充実プラン) | 1.150% |
住宅金融普及協会「住宅ローンの金利情報」(2023年10月)
※兵庫県で利用できる住宅ローン
金利が低い順番にランキングしたものですが、比較する際に注意しなければならない点があります。
10年固定の住宅ローンは、固定期間が終了した後の金利も含めて判断することです。
この記事では、変動金利や全期間固定金利と比べても分かりにくい固定期間選択型の主力商品である、10年固定住宅ローンを選ぶ際の注意点をまとめました。
●10年固定期間終了後の金利の決まり方
●10年固定住宅ローンのメリット・デメリット
●10年固定住宅ローンが向いている人
●10年固定住宅ローンで後悔する人
住宅ローン金利、10年固定終了後はどうなる?
10年固定住宅ローンの固定期間が終了したあとの金利はどのように決まるのでしょうか。その前提として、実際に適用される住宅ローンの金利がどのように決まるかを解説します。
住宅ローン金利の決まり方
実際に契約する住宅ローンの適用金利(実行金利ともいいます)は次のように決まります。
適用金利=基準金利(店頭金利)-引下げ幅(優遇幅)
金利は毎月変わる可能性がありますが、多くの金融機関は融資を実行する月の金利を適用金利としています。
基準金利(店頭金利)
住宅ローン金利の「定価」のようなもので、金融機関は金利タイプごとに基準金利を決めています。
基準金利は、経済状況や国の金融政策、金融機関の営業方針等で変わることがあります。
引下げ金利(優遇幅)
基準金利からの引き下げる(優遇する)金利。
引下げ金利が一律に決まっている金融機関もあれば、審査結果によって引下げ金利が変わる金融機関
があります。
10年固定期間終了後の選択肢

では、10年の固定期間が終了した後の金利はどうなるのでしょうか?
その際にとりうる選択肢は3つあり、それによって金利は異なります。
●変動金利になる
●再度、期間選択型の金利タイプを選びなおす
●他の金融機関に借り換える
順番にみてみます。
変動金利になる
10年間の固定期間終了後、何もしなければ変動金利になります。
ただし、その時点の変動金利がそのまま適用されるわけではありません。
前述の通り、適用金利は、基準金利と引下げ幅(優遇幅)で決まります。
つまり、10年固定期間終了後の金利は、その時点の10年固定金利タイプの基準金利と優遇幅で決まることになります。
分かりにくいと思いますので、auじぶん銀行を例に解説します。
10年固定の住宅ローン金利(auじぶん銀行)
以下は、10年固定期間中と11年目以降の基準金利と引き下げ幅です(2023年10月時点金利)
【当初10年間の金利】1.195%
【基準金利】3.270%
【当初固定期間の引き下げ幅】-2.075%
【11年目以降の金利】1.541%
【基準金利(変動金利)】2.341%※
【固定期間終了後の引き下げ幅】-0.8%
※基準金利が10年後も変わっていない前提
| 金利 | |
|---|---|
| 当初10年間 | 1.195% |
| 11年目以降(変動金利) | 1.541% |
固定期間終了後、それまでの1.195%から1.541%に上がります(約0.35%の上昇)。
これは固定期間と固定期間終了後の引き下げ幅(優遇幅)が違うためです。当初10年間の引下げ幅は2.075%に対し、固定期間終了後の引下げ幅は0.8%に縮小しています。
つまり、10年固定住宅ローン商品は、10年間低金利で固定する代わりに11年目以降の引下げ幅は少なくなる商品であるということです。
そして、住宅ローンを契約する時点で、固定期間終了後の引下げ幅は決まっています。
10年固定期間終了後の返済額の違い
これを返済額でいうとどれくらい変わるか?
下記事例での毎月の返済額は以下のようになります。
【借入金額】4,000万円
【返済方法】35年
【返済方法】元利均等返済(ボーナスなし)
| 毎月の返済額 | |
|---|---|
| 当初10年間 | 116,585円 |
| 11年目以降(変動金利) | 121,451円 |
返済額は約5,000円増えます。
つまり、10年間金利上昇がなくても、繰り上げ返済などしない限り毎月の返済額は増えるということです。
再度、期間選択型の商品を選ぶ
10年の固定期間終了時点で再度、固定期間選択型の商品を選ぶことができます。
再度10年固定の商品を選んだとした場合の金利は以下の通りです。
10年固定住宅ローンの金利(auじぶん銀行)
【当初10年間】1.195%
【基準金利】3.270%
【当初期間の引き下げ幅】-2.075%
【11年目以降】2.470%
【10年固定の基準金利】3.270%
【当初期間終了後の引き下げ幅】-0.8%
※10年間基準金利が変わっていない前提
| 借入金利 | |
|---|---|
| 当初10年間 | 1.195% |
| 11年目以降(10年固定金利) | 2.470% |
再度、固定期間選択型を選んでも、変動金利を選んだ場合と同様、金利の引下げ幅が縮小するため、適用金利は上がります。
当初10年間と11年目以降の返済額は以下のようになります。
【借入金額】4,000万円
【返済方法】35年
【返済方法】元利均等返済(ボーナスなし)
| 毎月の返済額 | |
|---|---|
| 当初10年間 | 116,585円 |
| 11年目以降(10年固定) | 135,124円 |
返済額は18,500円ほど上がります。
もし、10年間の間に経済情勢などの変化で基準金利が上昇した場合、11年目以降の金利、返済額はさらに上がる可能性があります。
ここまでみてきたように、10年固定住宅ローン商品は、当初10年間と11年目以降の金利の決まり方が異なります。
そして、金融機関によって基準金利も引き下が幅も異なります。
そのため、10年固定の住宅ローンだけでなく、固定期間選択型の商品を選ぶ際、11年目以降の金利も含めて判断する必要があります。
他の金融機関に借り換える
10年の固定期間が終了した時点で他の金融機関に借り換えた場合です。
その時点で、他の金融機関でより条件のよい住宅ローンがあれば借り換えを検討してもよいでしょう。
ただ、借り換えには注意点もあります。
●事務手数料や登記費用など諸費用がかかる
●借り換え先の審査をクリアする必要がある
●抵当権を抹消できる必要がある
借り換えといっても借換先の金融機関にとっては新規の借り入れと変わりません。
借り換え時点の収入や年齢、健康状態、物件の担保価値などを総合的に判断されますので、こういった条件をクリアする必要があります。
そのため、その時点で必ずしも借り換えができるかは分かりません。
住宅ローン10年固定終了後に金利の引き下げ交渉はできる?
10年の固定期間が終了後に金利が上昇した場合、金利の引き下げ交渉はできるのでしょうか?
金利交渉は可能ですし、引下げに応じてもらえる場合もある
金融機関としては、他の金融機関への借り換えを防ぎ、完済まで利用してもらうことが必要です。そのため交渉次第では、金利引下げが成功することもあるでしょう。
特に、借入している人の属性が良いく借入残高が多い場合は交渉はしやすいと考えらます。
ただし、他の金融機関の金利との比較は必要です。
- 複数の金融機関の金利を調べておく
- できれば他の金融機関の事前審査を通しておく
他行への借り換えには手数料や登記費用などの諸費用がかかりますが、金利の引下げがうまくいけばこういった費用も必要ありません。
交渉をするにあたりできるだけの準備はしましょう。
10年固定住宅ローンのメリット・デメリット
10年固定金利のメリット・デメリットについて解説します。
10年固定住宅ローンのメリット
10年固定宅ローンのメリットは、10年間低い金利で固定できる点です。
金利水準で考えた場合、10年固定金利は変動金利タイプより高くなります。ただ、10年固定だと低金利の恩恵を一定程度受けながら、金利上昇のリスクを回避できるメリットがあります。
10年固定住宅ローンのデメリット
10年固定住宅ローンのデメリットは、ここまで解説したように、固定期間終了時点の金利が上昇している点です。
多くの金融機関では、当初10年間の引下げ幅は、固定期間終了後、縮小します。また、10年後に変動金利になる、あるいはもう1度期間選択型の金利タイプを選び直すという選択ができるにしても、借入当初の基準金利が変わっている可能性があります。
また、毎月の返済額が増えた場合でも、変動金利のような金利上昇に対する緩和ルール(125%ルール)がありませんので、上昇した分の返済額は増えることになります。
つまり、10年固定住宅ローンは、固定期間終了後の金利が読めない商品ともいえます。
10年固定住宅ローンが向いている人
では、どういった人が10年固定住宅ローンに向いているのでしょうか。
自己資金に余裕がある
自己資金に余裕がある人は、固定期間終了時の金利上昇にも対応しやすい点で向いているといえるでしょう。
仮に金利が上昇していた場合、一定の資金で繰り上げ返済ができ、住宅ローン残高を減らすことができれば、金利上昇の影響を抑えることができます。
10年間だけ金利を固定したい
子どもの成長に合わせて仕事の復帰を考えている場合等、一定の期間だけ住宅ローンの返済を抑え、固定期間終了時点ではダブルワークで世帯収入の増加を見込める人は10年固定住宅ローンを検討しやすいでしょう。
住宅ローン控除を活用しながら資産運用に資金を回したい
低金利の状況では住宅ローンの金利負担より資産運用の運用益が上回ることは十分に考えられます。また、住宅ローンを組むことで住宅ローン減税や団信の保険効果があります。
ですので、積極的な資産運用で手元資金を活用しながら、固定期間終了時点に金利上昇していた場合は、繰り上げ返済で対応するということも考えられます。
10年固定住宅ローンで後悔しないための注意点
10年固定住宅ローンで後悔しないために以下の点を注意してください。
変動金利と固定金利で迷いとりあえず決める
住宅ローン選びで、変動金利と固定金利で迷って決めきれずに、中間的選択として10年固定住宅ローンを選ぶと後悔します。
10年固定住宅ローンは、当初は固定金利、その後変動金利を選択することもできますが、変動と固定の中間的な住宅ローン商品ではありません。
固定期間終了後の金利が読めないという点では、変動金利に近いといえるでしょう。
そのため、10年後の住宅ローン残高や貯蓄、家計の状況をしっかりと検討したうえで選ぶ必要がある商品です。
迷ったため、すすめられたまま何となく10年固定を選ぶことは避けましょう。
固定期間中の表面上の金利で決める
10年固定金利を選択するにしても、当初固定期間の金利だけで判断すると後悔します。
10年もしくはそれに近い返済期間を想定している人はそれでもかまいませんが、20年、30年の返済を想定している場合、当初10年よりそれ以降の金利水準が重要です。
11年目以降の各金融機関の基準金利、優遇幅も含め、しっかりと比較検討することが大切です。
まとめ
多くの方は、基準金利や引下げ金利を意識して住宅ローンを選んでいないと考えられます。ただ、特に10年固定金利含めた固定期間選択型住宅ローンは、固定期間終了後の金利が重要です。
また、住宅ローンを選ぶ判断材料は金利だけではありません。諸費用や団体信用生命保険など総合的に判断する必要があります。
- 10年固定金利ランキングの表面金利だけで判断してはいけない
- 適用金利は基準金利と引下げ金利(優遇幅)で決まる
- 10年固定期間終了後の選択肢
- 変動金利になる
- 再度、期間選択型を選ぶ
- 他の金融機関に借り換える
- 金利交渉してみる
- 固定期間終了後の金利を踏まえて決める