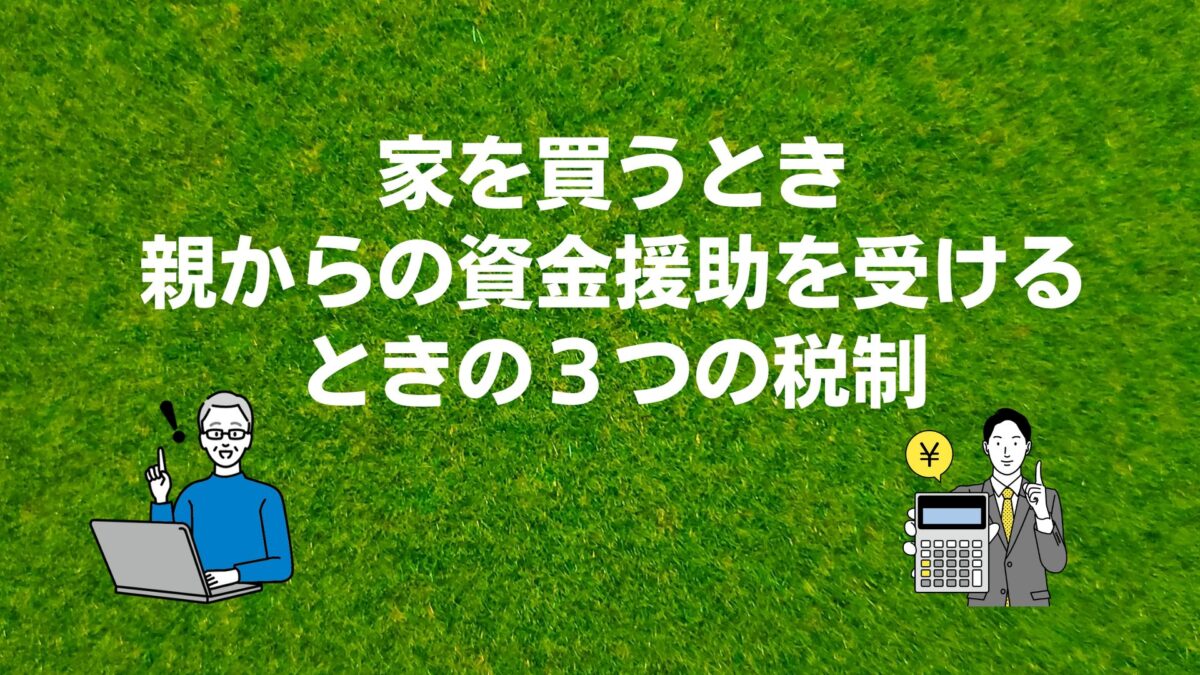投稿日:2023年4月16日 | 最終更新日:2023年10月11日
はじめに
家を買うとき…
資金援助が期待できそう…
親や身内から資金援助を受けて買われる方もいらっしゃいます。
一般社団法人不動産流通協会が令和3年から4年にかけて行った調査です。
親からの贈与を受けた割合は、全体の14.2%、
そのうち、
贈与の金額が1,000万円を超えた割合は、35.5%
2022年不動産流通に関する消費者動向調査
不動産流通経営協会
※首都圏1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)で令和3年4月1日~令和4年3月31日の間に購入した住宅の引渡しを受けた世帯を対象
資金援助はとてもありがたいことですが、住宅購入時に資金援助を受けることは(生前)贈与にあたり、贈与税の対象となります。
ですので、このような方もおられるのではないでしょうか。
- 税金がどれくらいかかるか不安
- 節税のためにどうすればいいの?
この記事では、住宅購入資金の援助を受けるときに使える制度と気をつける点について解説します。
住宅資金の援助を受けると税金はいくら?
そもそも住宅資金の援助を受けた場合、どれくらいの税金が発生するのでしょうか。
贈与税は暦年課税といい、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計に対して課税されます。
110万円の基礎控除がありますので、110万円を超えた贈与額に対して課税されます。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4500万円超え | 55% | 640万円 |
親から1000万円の資金援助を受ける予定だけど、贈与税はどれくらい?
1,000万円を親から資金援助を受けた場合
課税価格=1,000万円-110万円(基礎控除)
=890万円
890万円×30%(税率)-90万円(税額控除)
=177万円
贈与税額は177万円となります。
1000万円のうち177万円が税金って…
住宅取得資金贈与の非課税の特例
このように住宅資金の援助を受けた場合に必要となる贈与税ですが、その負担を軽減あるいはなくす制度が「住宅取得資金贈与の非課税の特例」です。
住宅取得資金贈与の非課税の特例は、
父母や祖父母などの直系尊属から住宅の新築、取得や増改築等の資金贈与を受けた場合に、非課税枠の範囲で贈与税がかからない制度です。
要件
住宅を新築、取得する場合の主な要件は以下のとおりです。
- 贈与者の直系卑属(子や孫など)である
- 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上
- 贈与を受ける年の年間所得が2,000万円以下である
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家に居住する、又は居住が確実なこと
- 住宅の床面積(登記簿上)が40㎡以上240㎡以下、かつ床面積の1/2以上が住宅用
- (中古住宅の場合)昭和57年1月1日以後に建築されたもの、もしくは地震に対する安全性の基準に適合するものであることが証明されたもの
新築もしくは中古住宅であっても、条件的には活用できる機会も多いと思われます。
非課税額
住宅取得資金贈与の非課税の特例の限度額は以下のとおりです。(図表2)
| 贈与の時期 | 省エネ等住宅※ | 一般住宅 |
|---|---|---|
| 2022年1月 ~2023年12月 | 1000万円 | 500万円 |
※省エネ等住宅とは、次のいずれかの基準を満たす住宅であることが証明されたもの
- 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上である
- 耐震等級2以上または免震建築物である
- 高齢者等配慮対策等級3以上である
省エネ住宅とそれ以外の住宅では、非課税額に大きな差があります。
直系尊属から住宅取得資金等の贈与を受けた場合の非課税(国税庁)
また、住宅取得資金贈与の非課税の特例は、暦年課税制度の110万円の非課税枠と併用することができます。
この制度を使うと、贈与税はどうなるの?
1000万円の資金援助を受けた場合、
●省エネ住宅を購入した場合
課税価格=1000万円-1000万円(非課税額)
=0で贈与税はかかりません。
●一般住宅を購入した場合(省エネ住宅以外)
課税価格=1000万円-500万円(非課税額)-110万円(暦年課税の基礎控除額)
=390万円
390万円×15%-10万円(税額控除)
=48万5千円(贈与税額)
暦年課税の177万円より税金の負担はだいぶ小さくなるね
注意点
住宅取得資金贈与の非課税特例について、いくつか注意点があります。
贈与をうける時期と入居時期
住宅取得資金贈与の非課税の特例を受けるためには、贈与を受けた翌年3月15日までに居住することが条件となっています。
ですので、贈与を受けて土地を購入し注文住宅を建てる場合に、工期が遅れ3月15日までに入居できない、もしくは、年末に贈与を受け翌年の3月15日までに引渡し間に合わせないといったことにならないように注意が必要です。
但し、入居見込みが証明できれば12月31日まで入居時期を遅らせることができます。
納税額がなくても確定申告が必要
この制度の適用を受けた結果、納付する税金がない場合であっても、翌年の確定申告時期(2月1日〜3月15日)に必ず申告する必要があります。
期限内に申告書を提出していない場合、この制度は使えず、前述の暦年課税による贈与税が課税されることになります。
2023年12月31日で終了!?
この制度で非課税となる限度額は年々縮小しています。
2019年時点では、
省エネ等住宅で3,000万円、一般住宅で2,500万円
2020年には、
省エネ等住宅で1,500万円、一般住宅で1000万円
そして、現在では、図表2(前述)のとおり、
省エネ等住宅で1,000万円、一般住宅で500万円
と限度額は年々縮小しています。
2019年は消費増税の影響緩和、2020年は新型コロナ対策という側面もありました。
そして、2022年税制改正大綱では、以下のような提言がされています。
経済対策として現在講じられている贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では、家庭内における資産の移転に対して何ら税負担お求めない制度となっていることから、そのあり方について、格差の固定か防止等の観点を踏まえ、普段の見直しと行っていく必要がある
令和4年度税制改正大綱(財務省)
そのため、この制度も2023年12月で終了する可能性があります。
相続時精算課税制度
もう1つ住宅資金の援助を受けた場合に使える制度として「相続時精算課税制度」があります。
相続時精算課税制度
贈与時点では、贈与された人は2,500万円まで贈与税を納める必要がなく、贈与した人が亡くなったときに、そのときの相続財産に贈与された財産(贈与時点の価額)を合計して相続税額を計算し、一括で相続税として納税する制度
もう少し分かりやすくいうと、「贈与する時点は2500万円まで非課税で、将来相続をするときに、相続財産と非課税にした分を併せて精算する制度」といえます。
つまり、住宅購入時点の贈与税の負担を軽減し、税金の負担を、贈与時点ではなく相続時点に先送りする制度です。
要件
住宅を取得、新築する場合の主な要件は以下のとおりです。
- 贈与者の直系卑属(子や孫等)もしくは推定相続人である
- 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家に居住する、又は居住が確実なこと
- 住宅の床面積(登記簿上)が40㎡以上かつ床面積の1/2以上が住宅用
- (中古住宅の場合)昭和57年1月1日以後に建築されたもの、もしくは地震に対する安全性の基準に適合するものであることが証明されたもの
非課税額
相続時精算課税制度は、最大2500万円まで非課税とすることができます。
また、住宅取得資金贈与の非課税の特例と併用することができ、一方110万円の暦年課税と併用することはできません。
ですので、「住宅取得資金贈与の非課税の特例」と「相続時精算課税制度」を使うことで、最大3500万円までの贈与について税負担をなくすことができます。
注意点
相続時精算課税制度を使う場合、いくつか注意点があります。
110万円の非課税は使えなくなる
1度相続時精算課税制度を使うと、以後110万円の非課税枠は使えなくなります。
つまり、以後、年間110万円以内の贈与におさえて非課税にしようとしてもできません。
ですので、毎年110万円の非課税枠をコツコツと使いながら、資産を移動させるといった形はとれなくなる点には注意です。
納税する額がなくても確定申告が必要
相続時精算課税制度を使って納付する税金がない場合であっても、住宅取得資金贈与の非課税の特例と同様、翌年の確定申告時期(2月1日〜3月15日)に必ず申告する必要があります。
まとめ
ここまで住宅資金の援助を受けた場合に使える制度ついて解説してきました。
こういった制度は、経済政策の一環として実施されていますので、有効に使いたいものです。
ただ、暦年課税と住宅取得資金贈与の非課税の特例は節税効果は見込めるものの、相続時精算課税制度については、税金の負担の先延ばしという意味あいが強く節税にはなりません。
それに加えて、暦年課税制度が2度と使えないというデメリットもあります。
ですので、相続時精算課税制度を使っても、相続時の基礎控除などで税金がかからないといった場合は利用価値があるかもしれません。
そういった点も含めて、制度の活用は慎重に判断してください。